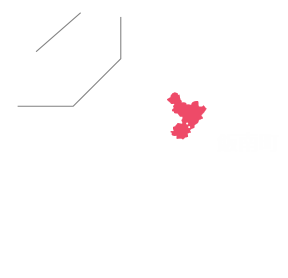ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
展示品紹介(雪かきすき)
雪かきすき
飯南町を中心とした地域で「ゆきかきすき」と呼ばれるこの道具は、主として屋根の雪を落とすために使用されてきたものです。
鳥取県東部を中心とした中国山地東部積雪地帯では「バンバー」「バンバン」、当町を含む中央積雪地帯では「スキ」「ユキカキスキ」、広島県芸北地域を中心とした西部積雪地帯では「ナセ」「ユキベラ」などと呼んでいます。
軒先に垂れ下がった雪を軒下から切り落としたり、地上の雪をすくいあげて除雪するという使用方法もありますが、一般的には屋根の上で使用します。軒先の雪を「直方体に切り」「雪かきすきの板の部分に乗せ」「屋根を滑らせ」「軒下へ落とす」といった使い方をしました。
鳥取県東部を中心とした中国山地東部積雪地帯では「バンバー」「バンバン」、当町を含む中央積雪地帯では「スキ」「ユキカキスキ」、広島県芸北地域を中心とした西部積雪地帯では「ナセ」「ユキベラ」などと呼んでいます。
軒先に垂れ下がった雪を軒下から切り落としたり、地上の雪をすくいあげて除雪するという使用方法もありますが、一般的には屋根の上で使用します。軒先の雪を「直方体に切り」「雪かきすきの板の部分に乗せ」「屋根を滑らせ」「軒下へ落とす」といった使い方をしました。

柄の長さ90cm・板の長さ56cm・幅22cm
材料は桜で江戸時代末に飯南町頓原で製作されたもの。
収蔵されている雪かきすきは桜材製が多数を占める。桜木は粘りがあり(折れにくく、磨耗が少ない)、ある程度重量があって(硬い雪を切りやすい)、雪のすべりが良い。

柄の長さ125cm・板の長さ65cm・幅20cm
材料は桜で江戸時代に飯南町頓原で製作されたもの。
この雪かきすきは地上の雪、主に軒下の通路に積もった雪、納屋・土蔵への通路などの除雪に使用された。現代のスコップ、シャベルを用いる要領で使用する。
雪すき考
雪すきは、杉や栗の木でも作ったが、桜の木で作るのが一番いいようです。雪すきの先端の平べったい部分は、幅が20センチはほしいからそれ以上の太さの木を探さなくてはいけません。山で桜の木を切り、雪すきの形に荒く削って家に持ち帰ります。生木を使うと後で割れたり、曲がったりするから最低でも一年くらい寝かせてから作ります。
材料に桜がいいのは、桜の木は、木を削った場合に表面がなめらかで、雪が付きにくいところにあります。その点ではブナも同じで雪が付きにくいが、材料調達や加工に難があるから、この雪すきは見たことがありません。杉などは加工しやすいが、年輪と年輪の境がやわらかく雪が付きやすいからあまり適さないと思います。
雪すきの先端の形や柄の長さは、各家さまざまにつくりました。全体の長さは、自分の身長より10センチくらい長めの180センチ、柄の長さが130センチ、板は長さが50センチ、幅20センチくらいのものが自分としては使いやすく思います。板の部分は長方形に削らず、すきの「肩」にあたる部分は幾分角度を付けて「なで肩」になるようにします。時には硬い雪に切り込むこともあるので、長方形の板に柄が付くような形では、柄や板の「肩」が壊れやすいからです。
近年、大雪が降ることが少なくなったといわれますが、年に一度や二度は屋根の雪降ろしをしなければなりません。雪降ろしには、やはり雪すきが便利だから、毎年捨てずにつかっております。スコップは「すくって投げる」ものですが、雪すきは、包丁みたいに「雪を切って」その固まりを「滑らせて落とす」道具です。雪の質にもよりますが、雪すきを使えばスコップで何杯も落とす量を一度に落とすことができます。スコップは柄や雪を乗せる部分が曲がっていたりするから、使いにくい面があるし、瓦をいためることもあります。
毎年、とかく、雪すきを使って「こがあな物をつこうとるのは、はぁウチほどかいのぉ」と思いながら、近所の軒先にも雪すきが立てすげてあるのを見て「やっぱり大雪の日はこれじゃあないとやれんのよぉ」と少し安心したような気分になります。
平成8年2月 山碕 昭三
材料に桜がいいのは、桜の木は、木を削った場合に表面がなめらかで、雪が付きにくいところにあります。その点ではブナも同じで雪が付きにくいが、材料調達や加工に難があるから、この雪すきは見たことがありません。杉などは加工しやすいが、年輪と年輪の境がやわらかく雪が付きやすいからあまり適さないと思います。
雪すきの先端の形や柄の長さは、各家さまざまにつくりました。全体の長さは、自分の身長より10センチくらい長めの180センチ、柄の長さが130センチ、板は長さが50センチ、幅20センチくらいのものが自分としては使いやすく思います。板の部分は長方形に削らず、すきの「肩」にあたる部分は幾分角度を付けて「なで肩」になるようにします。時には硬い雪に切り込むこともあるので、長方形の板に柄が付くような形では、柄や板の「肩」が壊れやすいからです。
近年、大雪が降ることが少なくなったといわれますが、年に一度や二度は屋根の雪降ろしをしなければなりません。雪降ろしには、やはり雪すきが便利だから、毎年捨てずにつかっております。スコップは「すくって投げる」ものですが、雪すきは、包丁みたいに「雪を切って」その固まりを「滑らせて落とす」道具です。雪の質にもよりますが、雪すきを使えばスコップで何杯も落とす量を一度に落とすことができます。スコップは柄や雪を乗せる部分が曲がっていたりするから、使いにくい面があるし、瓦をいためることもあります。
毎年、とかく、雪すきを使って「こがあな物をつこうとるのは、はぁウチほどかいのぉ」と思いながら、近所の軒先にも雪すきが立てすげてあるのを見て「やっぱり大雪の日はこれじゃあないとやれんのよぉ」と少し安心したような気分になります。
平成8年2月 山碕 昭三
 雪降ろし(平成18年1月)
雪降ろし(平成18年1月)