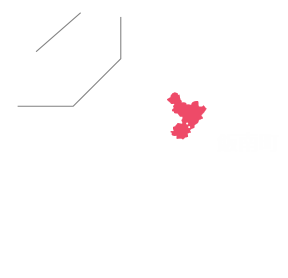ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
年表で辿る歴史の足跡(縄文時代~鎌倉時代)
縄文時代~鎌倉時代
| 西暦 | 時代 | 和暦 | 日本・島根 | 飯南町 |
|---|---|---|---|---|
| 約1万年前 | 縄文時代 | 三瓶山噴火 | 板屋3遺跡からおよそ1万年前の土器が見つかる | |
| 約4700年前 | 三瓶山噴火 | |||
| 約4000年前 | 八神に拠点的な集落が営なまれる(五明田遺跡) | |||
| 約3600年前 | 三瓶山噴火 | |||
| 約2300年前 | 弥生時代 |
稲作文化が大陸から伝わる このころ、銅剣・銅鐸がつくられる(荒神谷遺跡・加茂岩倉遺跡) |
八神の南・谷川(森遺跡群)や志津見(門遺跡)に大きな集落がつくられる |
|
| 約1700年前 |
古墳時代~ 飛鳥時代 |
このころ、大和朝廷の全国統一がすすむ | このころ集落が各地にできる(板屋3・森・門・神原遺跡など) | |
| 538 | このころ、百済から仏教が伝わる | |||
| 645 | 大化1 | 大化の改新 |
このころ、角井に大きな集落がつくられる(万場2遺跡) |
|
| 710 | 奈良時代 | 和銅3 | 平城京(奈良)に遷都 | |
| 733 | 天平5 | 『出雲国風土記』ができる | 風土記に志々乃村社・琴引山・荒鹿(草峠)坂・志都美径・多加山(大万木山)・神門川・石次野・野見野・木見野などの記載あり | |
| 770 | 宝亀元 | 松尾神社(赤穴八幡宮)が創建されたと伝える | ||
| 794 | 平安時代 | 延暦13 | 平安京(京都)に遷都 | |
| 1158 | 保元3 | 石清水文書に「赤穴別宮領」初出 | ||
| 1167 | 仁安2 | 平清盛が太政大臣となる(平氏隆盛) | ||
| 文治 | このころ、門脇教本 程原長徳寺を創建したと伝える | |||
| 1192 | 鎌倉時代 | 建久3 | 源頼朝が征夷大将軍となる(鎌倉幕府) | |
| 1207 | 建久2 | 源頼朝が由來八幡宮を祀ったと伝える | ||
| 1221 | 承久3 | 後鳥羽上皇隠岐へ配流(承久の乱) | ||
| 1271 | 文永8 | 赤穴太郎 赤穴庄50丁2反60歩を支配 | ||
| 1326 | 嘉暦元 |
赤穴八幡宮再建(赤穴庄地頭紀季實) |
||
| 1332 | 正慶1 | 後醍醐天皇隠岐へ配流 | ||
| 1333 | 正慶2 | 鎌倉幕府が滅ぶ |
この前後 赤穴庄の地頭 紀季實遂電 季實の二子遺領相続をめぐって争う |