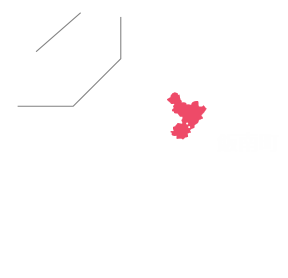本文
飯南町のできごと(明治~昭和39年)
明治~昭和39年
来島ダムが完成する
神戸川が江の川に接近する地域にダムを設け、二つの川の高低差を利用して水力発電を行う構想は戦前からあったといわれています。建設地の決定や住民との補償交渉など紆余曲折を経た後、最終的には飯南町下来島の神戸川に建設されることとなり、昭和29年に着工、2年後の昭和31年に完成となりました。高さ60メートル、長さ251メートル堰堤によっての堰き止められる神戸川の水量は2100万立方メートルあまり、美郷町の潮発電所に送られ、278メートルの標高差を利用した水力発電が行われています。


来島ダム 堰堤工事(昭和30年)
奥飯石神職神楽が島根県無形民俗文化財に指定される
昭和36年6月13日、飯石郡奥部の神社を中心に伝承されてきた奥飯石神職神楽が島根県の無形文化財に指定されました。神事の要素を残す七座に特徴があります。この神楽は飯南町を中心とする町内各神社において秋季のお祭りにあわせ奉納されています。

38・1豪雪、災害救助法発動される
昭和37年の12月末から降り始めた雪は翌年の2月中旬ごろまで降り続き、現在の国道54号は昭和38年の1月10日前後から完全に不通となり、奥飯石の地域は、まさに「陸の孤島」となりました。町内では食料品が商店から姿を消し、学校は休校となりました。2月8日には災害救助法が発動され、角井地区(飯南町角井)に航空自衛隊美保基地の輸送機によって緊急物資が投下されています。その後は、自衛隊、島根県などの懸命な除雪活動によって2月25日、松江・広島間が40日ぶりに全線開通し、3月6日には掛合(雲南市掛合町)から布野(三次市布野町)間のバスが58日ぶりに運行されました。昭和37年12月29日から38年2月10日までの赤名における降雪量は10メートル30センチを記録しています。
 動けなくなった車
動けなくなった車  赤名市街(昭和38年2月)
赤名市街(昭和38年2月)
下来島のボダイジュが島根県天然記念物に指定される
9月16日 国道54号赤名トンネル完成
昭和26年、島根県、広島県の関係21市町村、議会関係者、企業関係者が布野村(広島県三次市布野町)に会し、「赤名峠隧道工事期成同盟会」が設立されました。これを契機として広島松江間の国道改修を要望する「広島松江線国道改修期成同盟会」が発足し、昭和38年から国道54号の改修工事が始まることとなります。これに先立ち、赤名トンネルの工事は昭和36年に着手され、三年余の歳月と3億8千万円あまりの工事費をもって完成し、4.5キロメートルの赤名峠越えの道のりは2.8キロメートルに短縮されました。
古来より、山陰と山陽の交通のみならず、飯石郡奥部の人々の生活や文化までも閉塞させていた感のある赤名峠にトンネルが貫通したことは、地域住民の悲願達成でもあり、新しい時代の到来を予感させる大きな出来事でした。
 開通式(昭和39年)
開通式(昭和39年)  貫通場所で対面する両県知事(昭和38年)
貫通場所で対面する両県知事(昭和38年)
9月21日、22日東京オリンピック聖火通過
昭和39年9月21日午後五時、完成したばかりの赤名トンネルを通過し、東京オリンピックの聖火が到着しました。赤来町役場(当時)で一泊した聖火は翌22日、赤名中学校で出発式を終えた後、赤来、頓原両町内をリレーされ、晴雲トンネルを通過し、午前9時39分に無事、掛合町恩谷(雲南市掛合町恩谷)に到着しました。
 町内での聖火リレー
町内での聖火リレー  聖火の出発式
聖火の出発式